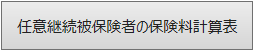健康保険への加入について
健康保険への加入 (2)
採用後、試用期間中の勤務状態が良好であれば、その後正社員として引きつづき雇用するケースが多くみられますが、これは2ヵ月以内の試用期間を定めて採用する臨時採用とは異なり、一般的には試用期間を定めていない採用と理解されます。したがって、試用期間を定めた場合であっても、当初から被保険者となります。
健康保険の適用については、事業所から労務の対償として報酬を受けている場合、その事業所に使用される社員として被保険者の資格を取得するものとされています。ただし、被保険者として取り扱うかどうかは、その身分関係だけでなく使用関係の実態により判断します。その取り扱い基準は、おおむね次のとおりです。
- パート採用の場合は、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、その事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の4分の3以上であること
- 上記に該当しない場合でも、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して、事業所との間に実態的かつ常用的な使用関係があること
特定適用事業所 (18)
4分の3基準を満たさない短時間労働者は、4要件全てを満たした場合に被保険者資格を取得します。
●4要件とは
①週の所定労働時間が20時間以上ある
②雇用期間が2カ月を超えて見込まれる
③賃金の月額が8.8万円以上である
④学生ではない(休学中、夜間学部等を除く)
被保険者に係る短時間労働者であるかないかの区別に変更があったときは、当該事実が発生した日から5日以内に、「健康保険被保険者区分変更届」をご提出ください。
法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。
「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、
同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12 か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。
遡及取消にはなりません。また、特定適用事業所を不該当とする場合は、通常の手続きと同様に労使の合意が必要となります。
4週5休制等のため、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない場合等は、当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出します。
1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します(1年間を52週とし、1か月を12分の52週とし、12分の52で除すことで1週間の所定労働時間を算出する)。
1年の所定労働時間を52で除して算出します。
夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められている場合や、繁忙期間中の特定の月の所定労働時間が例外的に長く定められている場合等は、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して、1週間の所定労働時間を算出します。
実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等※が該当しますが、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は対象から除かれることとなります。
※(参考)厚生年金保険法施行規則第9条の6に規定する学生
・高等学校に在学する生徒
・中等教育学校に在学する生徒
・特別支援学校に在学する生徒
・大学(大学院を含む)に在学する学生
・短期大学に在学する学生
・高等専門学校に在学する学生
・専修学校に在学する生徒
・各種学校に在学する生徒(修業年限が1年以上である課程を履修する者に限る)
・上記の教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
雇用時に2か月を超える見込みであった場合、結果として雇用期間が2か月未満になったとしても、被保険者の資格取得を取り消しはできません。
雇用期間が2か月以内である場合であっても、次の(ア)(イ)のいずれかに該当するときは、定めた期間を超えることが見込まれることとして取り扱うこととし、最初の雇用期間を含めて、当初から被保険者の資格を取得します。
(ア)就業規則、雇用契約書等その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていること
(イ)同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により2か月を超えて雇用された実績があること
ただし、(ア)(イ)のいずれかに該当するときであっても、労使双方により、2か月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないこととして取り扱います。
月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき、要件を満たすか否かを判定します(年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。)。
月額賃金8.8 万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。ただし、以下の①から④までの賃金は算入されません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
日給や時間給によって賃金が定められている場合には、被保険者の資格を取得する月前1月間に同じ事業所において同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者が受けた報酬の額の平均額を算出します。
※ 「同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者」とは、同一事業所内の同一の部署に勤務し、時間単価や労働日数等の労働条件が同一の方を指します。
ただし、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者がいないような場合は、個別の雇用契約等に基づいて月額賃金を算出します。
1週間の所定労働時間で算出した賃金額に12分の52を乗じて算出します。
資格確認書について
資格確認書 (5)
「資格確認書」とはマイナ保険証を保持していない方に交付するもので、病院で提示することで保険適用の取り扱いとなります。
資格確認書の有効期限は、発行年度から「3年目の3月末日」です。
例)令和7年(2025)1月発行→令和9年(2027)3月末期限
令和7年(2025)4月発行→令和10年(2028)3月末期限
マイナ保険証により受診できている方へは原則「資格確認書」は発行できません。ただし、マイナンバーカードの紛失などにより「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方」については、発行が可能です。
有効期限内に退職する場合や扶養削除の場合には事業所経由でご返却ください。有効期限経過後には、本人において破棄してください。
マイナ保険証で受診が可能な方については、マイナポータルより「医療保険の資格情報」のPDFファイルをダウンロードまたは印刷したもの、「資格情報のお知らせ」いずれかで受診が可能です。
保険料の決定・変更・徴収
算定基礎届・月額変更届 (4)
健康保険法では、被保険者の資格を取得したとき、個人ごとに「標準報酬月額」が決定されます。その後は昇給や降給などで従前の標準報酬と比べて、各月の報酬の「支払基礎日数」が17日以上ある3ヵ月間の報酬総額の平均額による標準報酬に、2等級以上の差が出るなど著しい変動があった場合、「月額変更届」により改定することになっています。
ところが、昇給・降給があったにもかかわらず、「月額変更届」の要件に該当しない方は、資格取得時の標準報酬と実態がかけ離れてしまいます。
そのため、年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について報酬の届出を行い標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届出を「算定基礎届」といいます。「算定基礎届」の提出については、健康保険法に定められており、事業主は、必ず提出する義務があります。
報酬を計算する基礎となった日数を「支払基礎日数」といいます。日給制の場合は、稼働(出勤)日数が「支払基礎日数」となります。時給のパート・アルバイト社員もこれに該当します。月給制の場合は給料計算の基礎が暦日で、日曜日や有給休暇も含まれ、出勤した日数に関係なく暦の日数が「支払基礎日数」となります。たとえば、4月21日から5月20日までの給料を5月25日に支払う場合は、5月の「支払基礎日数」は30日となります。ただし、欠勤日数分について給料が控除される場合は、事業所の欠勤減額の規定に基づいて計算した日数が「支払基礎日数」となります。
| 例 | 5月の支払対象期間 | 5月の支払基礎日数 |
|---|---|---|
| (1)20日締め当月25日払い | 4月21日~5月20日 | 30日 |
| (2)20日締め翌月5日払い | 3月21日~4月20日 | 31日 |
7月・8月・9月を改定月とする「月額変更届」を提出する方については、「算定基礎届」の提出は不要です。7月の随時改定に該当する場合は、「算定基礎届」を提出せずに「月額変更届」を提出してください。
8月、9月の月額変更予定者は、後日、「月額変更届」を提出してください。ただし、8月・9月の月額変更予定者に支払われた実際の報酬額が見込みより少なく2等級以上の差が生じなかったり、「支払基礎日数」が17日未満のため月額変更に該当しなくなったりした場合は、「算定基礎届」を提出していただきます。
算定基礎届の詳細についてはこちら
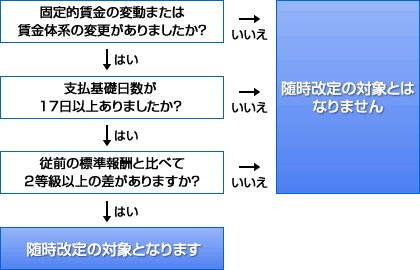
固定的賃金の変動月以降引き続く3か月の平均が1,415,000円以上の場合、 等級差は1等級差しかありませんが、随時改定の対象となり、改定後は標準報酬月額の上限である1390千円となります。
定時決定における年間平均での届出 (11)
業務や職種の特性上、基本的に毎年4月~6月が繁忙期に当たるため、4月~6月までの期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動のおこることが想定されることをいいます。
たとえば単年度のみなど、業務の一時的な繁忙による報酬の増加等は対象外になります。
繁忙期が1年間に複数回あったとしても、4月~6月までの報酬月額の平均と、前年7月~当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象となります。
報酬変動が起こる部署を単位として対象とします。適用事業所全体について報酬変動がおこる場合は、適用事業所に勤務する従業員全体が判断対象となりますが、本問の事例では、従業員全体ではなく、繁忙期に当たる部署のみを判断対象とします。
支給基礎日数が17日以上の月を対象として報酬月額の平均を計算します。パートやアルバイトの方は、支払基礎日数が15日以上の月を対象として計算します。
なお、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月および一時帰休に伴う休業手当を受けた月は計算対象から除外します。
4月~6月までの間の報酬月額の平均を計算するに当たっては、定時決定を行う際の従来からの取り扱いと同様となります。
前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算するに当たっては、それぞれ以下のような取り扱いになります。
- 前年6月分以前に支払うべきであった給与の遅配分を前年7月~当年6月までに受けた場合 その遅配分に当たる報酬の額を除いて、報酬月額の平均を計算します。
- 前年7月~当年6月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が当年7月以降に支払われることになった場合 その本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算します。
当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがあるかどうかによって判断します。
- 当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがある場合
保険者算定のルールを適用します。4月~6月までのうち、一時帰休に伴う休業手当等が支払われなかった月における報酬月額の平均と、前年7月~当年6月(一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は除く)までの報酬月額の平均を比較して、標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じれば対象とします。 - 当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがない場合
保険者算定のルールを適用しません。
前年7月~当年3月までの間に、少なくとも1ヵ月以上確保されている必要があります。
随時改定と同様に、以下の事例に該当する場合は、1等級差でも保険者算定の対象になります。
<健康保険>
- 4月~6月の報酬月額の平均と前年7月~当月6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が141.5万円以上、もう片方の月額が129.5万円以上135.5万円未満の場合
- 4月~6月の報酬月額の平均と前年7月~当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が5.3万円未満、もう片方の月額が6.3万円以上7.3万円未満の場合
今回追加した事由に基づく保険者算定に関する申立を事業主が行うことによって、被保険者に不利益が生じることのないよう、被保険者の同意を必要とします。被保険者の同意がない場合は、その同意がなかった被保険者の標準報酬月額についてのみ、通常の報酬月額の算定に基づき標準報酬月額を決定します。
各々2セット作成する必要はなく、たとえば原本を事業主が保管し、写しを日本年金機構および健康保険組合に提出する取り扱いとして差し支えありません。ただし、日本年金機構および健康保険組合に提出する同意書は同じ内容であることが必要です。
被保険者が毎年同意をするとは限らないので、毎年提出していただきます。
随時改定における年間平均での届出 (11)
業種や職種の特性上、基本的に特定の3ヵ月が繁忙期に当たるため、当該期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動の起こることが想定されることをいいます。
例えば、定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定、例年発生しないが業務の一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定や、転居に伴う通勤手当の支給による改定等は、随時改定における年間平均を計算の基礎とした保険者算定の特例の対象外です。
なお、産前産後休業や育児休業を終了した際の月額変更も対象外です。
改定要件に該当しない事由の例
- 定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定
- 例年発生しないが業務の一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定
- 転居に伴う通勤手当の支給による改定
- 非固定的賃金の支払いの影響ではなく、単に固定的賃金額が大きく増減したことによる改定
繁忙期が1年間に複数回あったとしても、昇給月から継続した3ヵ月の報酬の平均と、昇給月前の継続した9ヵ月および昇給月以後の継続した3ヵ月の間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象となります。
特定の時期に報酬変動が起こる部署や役職を単位として対象とします。
支払基礎日数が17日以上の月(短時間被保険者の場合は支払基礎日数が11日以上の月)を対象として報酬月額の平均を計算します。
なお、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月および一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は計算対象から除外します。
また、月の途中に入社した場合の入社月や再雇用により資格の得喪が生じた月以前の月については、計算の対象となりません。
各月の被保険者の区分(短時間被保険者であるかないか)に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象月となるかならないかを判断します。
なお、月の途中に区分変更があった場合は、当該月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により、当該月が算定の対象になるかならないかを判断します。
少なくとも1ヵ月以上必要です。なお、入社して1年未満の者についても対象となります。
昇給月または降給月前の継続した9ヵ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月までの間に、今回追加した保険者算定の要件を満たす部署に異動した場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算します。
報酬月額の年間平均を計算するに当たっては、具体的には、それぞれ以下のように取り扱います。
- 昇給月または降給月前の継続した9ヵ月以前に支払うべきであった給与の遅配分を年間平均の計算対象月に受けた場合 → その遅配分に当たる報酬の額を除いて、報酬月額の平均を計算する。
- 昇給月または降給月前の継続した9ヵ月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が昇給月または降給月から4ヵ月目以降に支払われることになった場合 → その本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算する。
昇給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級または下回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行いません。
また、降給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級または上回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行いません。
必ずしも申立書を提出させる必要はありません。申立てがない場合は通常の報酬月額の改定のルールに基づいて標準報酬月額を決定することになります。
賞与支払届 (4)
同じ月に支払われた賞与の金額を合算して、後に支払われた日を支給日として届け出ます。
すでに1回目の届出を提出済の場合は、訂正届(用紙のみの対応)を提出してください。
資格喪失月に支給された賞与は保険料納付の対象になりませんが、喪失日の前日以前に支給された場合には賞与支払届の提出が必要です(ただし、資格取得された同月に資格喪失される場合には、保険料納付の対象となります)。
【例】退職日:6月15日(資格喪失日:6月16日)の場合
①賞与支払日:6月10日 ⇒ 保険料納付なし、届出は必要
②賞与支払日:6月20日 ⇒ 保険料納付なし、届出は不要
産前産後休業期間中の保険料免除 (5)
「産前・産後休業(終了)変更届」の提出が必要です。実際の出産日が出産予定日と異なったことで、産後56日目となる休業終了日が変更になる[出産が早まった場合は産前42日(労務に服していない日も変更可能)]ため、届出が必要です。
原則必要ありません。例外として以下に該当した場合は必要です。
産後休業終了から1か月を経過した場合
(1)遅延理由書 (2)賃金台帳 (3)出勤簿
対象となります。出産のために休んでいれば、有給休暇であっても保険料免除の対象となります。有休、公休、欠勤は問いません。
産前休業開始日(産前42日のうち労務に服していない日)から休業終了日以内に提出してください。休業開始日が到来する前は受付できません。
育児休業期間中の保険料免除 (10)
育児休業を取得できるのは、男女雇用労働者と法に明記されているため、夫でも免除の対象になります。
対象となります。育児等のために休んでいれば、有給休暇であっても保険料免除の対象となります。有休、公休、欠勤は問いません。
14 日の要件による免除の仕組みは、開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する育児休業等についてのみ適用されます。したがって、「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、その月の月末日が育児休業等期間中であるか、その月の月中に当該育児休業等とは連続しない別途の育児休業等(14日以上)を取得している場合にのみ免除となり、ご質問の内容では免除になりません。
○開始日から終了予定日までの日数(当該育児休業等が出生時育児休業である場合、「就業日数」を除いた日数)を当該育児休業等に係る「育児休業等日数」とします。
○月内に開始日と終了予定日の翌日がともに属する育児休業等が複数ある場合、当該月の「合計育児休業等日数」が14 日以上であれば(休業は連続していなくても)、当該月の保険料が免除されます。
育児休業等日数は、ある育児休業等の開始日から終了予定日までの日数(当該育児休業等が出生時育児休業である場合、開始日から終了予定日までの日数から就業日数を除いた日数)をいい、その間に土日等の休日、有給休暇など労務に服さない日が含まれていても、育児休業等日数の算定に当たり差し引くことはせず、育児休業等日数に含まれます。
労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に、一時的・臨時的(災害や突発的な事態への対応等、あらかじめ予定していない場合)に、その事業主の下で就労可能とされているため、こうした一時的・臨時的な就労については、育児休業等日数の算定から除く必要ありません。 ただし、育児休業等開始当初よりあらかじめ決められた日に勤務するような場合は一時的・臨時的な就労には該当せず、育児休業等をしていることとはなりません。
賞与保険料の免除対象外とする1月以下の育児休業等期間の算定については、暦によって計算します(例えば、11 月16 日から12 月15 日まで育児休業等の場合、育児休業等期間はちょうど1月であるため、賞与保険料の免除の対象外となります)。
連続して複数回の育児休業等を取得している場合は、1つの育児休業等とみなすこととなるため、合算して育児休業等期間の算定に含めることとなります。
育児休業等期間終了後であっても、一定期間(育児休業等の終了日から起算して暦による計算で1 ヶ月以内)であれば理由書等の添付がなくても、受け付け可能となります。一定期間経過後の届出については、理由書や出勤簿の提出が必要になります。
複数回の育児休業等の取得届出をまとめて提出するのではなく、育児休業等を取得する都度提出します。
○ ただし、開始年月日と終了年月日の翌日が同じ月に属する複数の育児休業等を取得した場合で、通算して、14 日以上となる場合には、複数回の育児休業等の取得届出をまとめて提出することが可能です。この場合、それぞれの育児休業等開始年月日、育児休業等終了年月日、育児休業等取得日数及び就業日数を取得届出に記載します。
被扶養者として申請する
収入のある被扶養者の申請 (5)
原則として収入のすべてです。課税対象かどうかに関わらず、パート・アルバイト等の給与収入、公的年金、私的年金、雇用保険の失業給付、家賃等の不動産収入など、継続的に生じるすべての収入が対象となります。
自営業・個人事業主の場合は所得ではなく、総収入から経費を差し引いた金額が審査対象の収入となります。
※経費として差し引く金額は、確定申告の内容等を基に健康保険組合にて判断します。
ただし、退職金、不動産や株式などの売却益など、一時的に発生するものは除きます。
年収とは、扶養の申請時から1年間の見込額を意味します。例えば、過去の収入が130万円を超えていたとしても、その実績から判断するのではなく、申請日以降に継続的な収入があるかどうかで判断します。
| 対象の年齢 | 収入限度額 | 給与収入等がある場合 (参考目安として) |
|
60歳未満 |
年間収入 130万円未満 |
月額108,334円未満 (年額130万円÷12か月) |
|
19歳以上 |
年間収入 150万円未満 |
月額125,000円未満 (年額150万円÷12か月) |
|
60歳以上 |
年間収入 180万円未満 |
月額150,000円未満 (年額180万円÷12か月) |
上記月額について
給与収入の場合:交通費、賞与等を含む総収入額
年金収入の場合:介護保険料控除前の年金支払額
税法上の扶養親族と健康保険法における被扶養者では、収入基準(※)や対象となる親族の範囲が異なっており、認められるとは限りません。当組合へ届け出いただき、審査のうえ判断させていただくことになります。
(※)税法上の扶養控除対象者は、前年(1月から12月)の年間収入で判断しますが、健康保険法における被扶養者は申請時点より、今後一年間の収入見込みで判断します。
アルバイトやパート等で収入のある家族を被扶養者として申請される場合、一覧表にある添付書類のほかに、アルバイト先またはパート先の事業主の証明のある「雇用条件証明書」が必要です。※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です。
なお、その家族がアルバイト先またはパート先の会社で加入している健康保険の被保険者となっている場合、または交通費を含めた月平均収入額が収入限度額以上となる方は、被扶養者の認定対象外となります。
マイナンバーを被扶養者申請時に同時に提出いただくことで、政府管轄のネットワークシステムに即座に登録を行うことができ、被扶養者の認定に必要な「収入(所得)」「年金」「雇用保険」「住民票」等の情報をマイナンバーに紐づけて入手する事が可能です。当組合では、組合員の皆様からご提出いただいたマイナンバーを最大限活用し、添付書類入手にかかる手間や手数料を省くことで、サービスの向上と業務効率化を図ることを目的としています。
19歳以上23歳未満の収入要件 (4)
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く)を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなりました。
これを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)の被扶養者認定の要件の見直しを行いました。
なお配偶者とは、健康保険法等における取り扱いと同様、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。あくまでも年齢によって判断します。
年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから今後1年間の収入を見込むこととなります。
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
退職した家族の被扶養者の申請 (4)
雇用保険の失業給付の目的は、その失業中の生活の安定を図ることにあり、失業給付受給中の方は、この失業給付によってある程度生活が保障されているといえます。また、失業給付を受給中ということは、受給者自身が就職することを目的としていることから、その状態は一時的なものと考えられます。よって失業給付受給者は、現実には被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、一般的には失業給付受給期間中は、被扶養者とは認められないことになります。
※「基本手当日額」が、被扶養者の収入基準内(19歳以上23歳未満:4,167円未満、60歳未満:3,612円未満、60歳以上:5,000円未満)である場合には、例外的に被扶養者となることができます(ただし他の収入と合わせると収入基準を超える場合を除く)。
出産手当金は、一定期間(産前42日間、産後56日間、計98日間)の生活の安定を図るために給付されます。よって、出産手当金を請求できる期間は、被扶養者として認められません。
被扶養者の対象となります。
失業給付の受給意思があっても、出産や病気により直近で就業することができず、失業給付の受給延長をされている期間については認定対象となります。
「雇用保険受給延長通知書」の写しをご提出ください。
(出産予定で退職から1か月以内の申請に限り、「①離職票1・2の写し ②母子手帳の出産予定日記載箇所の写し」で代用可能です。)
※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です。
※ただし、疾病による傷病手当金・出産による出産手当金等の給付金が支給されている場合は、対象外となる場合があります。
給付制限がある方であれば、給付制限期間中の認定が可能です。
ハローワークにて手続き後に交付される「雇用保険受給資格者証」の写しをご提出ください。
※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です。
失業給付の受給開始後は、保険証のご返却と共に被扶養者異動(削除)届のご提出が必要です。
ただし、失業給付の受給額によっては、受給開始後も被扶養者として継続が可能です。
夫婦共同扶養の子供の被扶養者の申請 (3)
被扶養者の人数に関わらず、年収の高いほうの被扶養者となります。夫婦の年間収入の差が1割以内である場合は、届出をいただいた方を主たる生計維持者として手続きをいたします。したがって、届出をいただいた方の被扶養者となります。このとき、被保険者にすでに被扶養者となっている子供がおり、被保険者が育児休業等を取得中である場合には、特例的に先に認定されていた子供は、異動(削除)させないこととなっております。
一般的に産後休業・育児休業中は給与収入がなくなることから、出産手当金および雇用保険から支給される育児休業給付金を見込んだ額と夫の収入を比較し、収入が高い方の扶養に入れていただくこととなります。
産前産後休業期間:出産手当金
育児休業期間 :180日目までは標準報酬月額×67%(上限の額を超える場合は上限額)
181日目からは標準報酬月額×50%(上限の額を超える場合は上限額)
※育児休業給付金には上限があります。上限額は厚生労働省より示される金額を参照しています。
※上記以外にも賞与の支給予定がある場合は収入に含めます。
申請される際には、夫の収入の分かるもの(源泉徴収票、所得証明書、確定申告書の写し、雇用条件証明書等)のご提出が必要となります。
マイナンバーで照会ができるため、添付書類は不要です。ただし、同居日や離婚日で認定を希望する場合は、根拠となる日付を確認できる書類(住民票、戸籍謄本等)をご提出ください。
別居している被扶養者の申請 (7)
同一世帯とは、被保険者と住居・家計をともにしている状況をいいます。この場合、戸籍が同じであることは必ずしも必要ではなく、また、被保険者が世帯主であることも必要ではありません。
銀行振込の場合は振込み受領書等、現金書留の場合は郵便局で発行される控え、インターネットでの振込みの場合は振込み画面のハードコピー等をご提出ください。
証明書には「誰から誰へ、いつ、いくらの送金がされているか」の確認ができることが必要になります。
*原則、直近1ヶ月(1回)分の証明を添付して下さい。
手渡しをする現金を定期的に引き落としたことがわかる預金通帳の写しをご用意ください。
※1回のみでは実質的に生計維持をしていることの判断をすることが困難なことから、3回以上の実績が必要となります。
単身赴任による別居の場合は、送金証明のご提出は不要です。被扶養者異動届に別居先の住所をご記入ください。
※別居から同居に戻った際には「被保険者住所変更届」「被扶養者住所変更届(別居→同居の申請)」のご提出が必要です。
進学による別居の場合は、送金証明・住民票は、原則不要です。ただし、一般的に就労している年齢(23歳以上)の被扶養者等について、収入確認書類の添付を求める場合がございます。
被保険者からの送金によって、生計が成り立っている状況下においては被扶養者として継続可能です。ただし、被扶養者に収入がある場合、被扶養者の収入を超える金額を仕送りしていることが必要です。
また、被扶養者住所変更届のご提出が必要となります。
入院中は、一時的に別居の状態となりますが、生活の本拠は依然として家族の住んでいる場所にあると考え、同居として取り扱います。
海外に居住する被扶養者の申請 (4)
これまで日本で暮らしており、渡航目的に照らし、今後日本で生活する蓋然性が高いと認められる場合です。具体的には「渡航目的が就労でないこと」「渡航が一時的であること」が基本となります。
ありません。渡航目的が留学であれば、「例外要件」に該当します。
ビザに有効期限がある場合は、原則として「一時的」と判断して差し支えありません。ビザに有効期限がない場合は、内容を含め健保組合にて総合的に判断します。
海外赴任中に生まれた被保険者の子どもや、現地で結婚した配偶者などで、海外赴任後に日本で生活すると予定されている被扶養者が該当します。
氏名や住所が変わった
氏名変更届 (2)
氏名・生年月日・続柄などは、戸籍上の正しいものを「被保険者氏名変更(訂正)届」、または「被扶養者(異動)届」に記入してTJKに提出しなければなりません。
住民票など変更前と変更後のお名前の分かる公的な書類をご提出ください。
住所変更届 (2)
住所変更のあった場合は自身で訂正することができます。ただし、資格確認書に記入してよいのは住所欄だけで、その他のことを記入したり、勝手に直したりすることはできません。なお、住所変更があった場合は、必ず事業主に申し出てください。所定の手続きが必要となります。
資格確認書裏面「住所」欄に余白があるときは変更した住所を自署してください。余白がないときは、ラベルシールを貼るなどして対応してください。ラベルシールがない場合は、事業所を通じて当組合にご依頼いただきますようお願いいたします。
退職した
健康保険の資格喪失 (5)
退職すると被保険者の資格を失います。資格確認書の交付を受けている場合は、退職日の翌日以降すみやかに事業主に返納してください。返納するのは、発行されている本人・家族の資格確認書すべてです。
退職した方が、1日の空白もなく同一の事業所において引き続き再雇用された場合、被保険者の資格は継続することとなっておりますが、60歳以上で退職された方については、退職日の翌日に被保険者資格を再取得する取り扱いが可能です(この取り扱いを希望しない場合には、提出する必要はありません)。
なお、上記に該当する場合は、「被保険者資格喪失届」「資格確認書 ( 交付を受けているとき)」の他に、「被保険者資格取得届」と退職再雇用であることを確認できる下記書類の添付が必要となります。
- 就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるもの)
- 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの)
- 「退職日」「再雇用された日」に関する事業主の証明書
※ 上記書類のうち、①+②、もしくは③の提出が必要となります。
健康保険の給付は、たとえ被扶養者に対する場合でも、被保険者に対する支給となっています。そのため、被保険者の死亡等で被保険者資格を失うと、給付を受けられる人がいなくなりますので、被扶養者が受診中でも給付を打ち切られることになります。
退職後にTJKの資格確認書を使ったということは、本来TJKの被保険者資格がない方が不正にTJKの保険給付を受けたということになります。この場合、後日自己負担額を除く全額をTJKから請求することになります。退職後は、TJKの被保険者資格を喪失した後に加入した健康保険をご利用ください。これは、被扶養者である家族が資格を喪失したときも同様です。
退職日までに2ヵ月以上の継続した被保険者期間がある場合、任意継続被保険者制度に加入することができます。
申請する場合は、退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」をダウンロードし、 必要事項にご記入のうえ、「東京都情報サービス産業健康保険組合」 までご送付ください(必着)。
- 期日を超えますと、受理できませんので、早めにお手続きください。
引き続きTJKに加入する(任意継続被保険者制度)
任意継続被保険者制度 (11)
下がりません。任意継続の保険料は、「退職時の等級」もしくは「前年9月のTJKの平均等級」のうち、低い方が適用され決定します。決定された保険料は、原則加入している間に変更となる事はありません。
ただし、健康保険料率、介護保険料率は変わることがあり、料率の変更により保険料金額が増減することがございます。
※保険料率は毎年2月下旬に決定されます。
その方の収入状況により保険料は異なるため、一律にお答えすることができません。国民健康保険は原則、前年の所得金額に応じて決定され、任意継続保険料は退職時の等級で決定されます。国民健康保険の保険料金額は、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。任意継続の保険料金額は、保険料額計算表をご覧ください。
人数によって変わることはありません。被扶養者からは保険料をいただいていないため、ご本人のみの負担になります。
「就職」は任意継続の資格喪失事由に該当します。健康保険の切り替え(任意継続の資格喪失手続き)をいたしますので、 当組合に下記の書類をご提出ください。
- 「任意継続被保険者資格喪失申出書」
- 新しく加入した健康保険組合の加入情報が分かる書類(資格情報のお知らせのコピーまたは資格確認書のコピー)
- TJKの「限度額適用認定証・資格確認書 」 (交付を受けている方のみ)
内容確認のうえ、保険料の還付対象者には、後日ご返金いたします。
なお、就職先の「資格取得日」以降は任意継続保険で医療機関等の受診ができませんのでご留意ください。
- 資格確認書の返却について
当組合の資格確認書は、就職先の「健康保険の資格取得(適用)日」より使用できません。必ずご返却ください(ご家族分含む)。
「送付先」 〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
東京都情報サービス産業健康保険組合 適用グループ
当組合に「被扶養者異動届」とお子様の「限度額適用認定証・資格確認書」(交付を受けている方のみ)を併せて郵送してください。
確定申告の際は、任意継続保険料に関する添付書類(領収書等)は不要です。その年に納めた合計額を申告することで問題ありません。確定申告に関するご不明点は、お住まいの管轄の税務署にお問い合わせください。
当組合では、2年間の任意継続期間が満了となり資格喪失する前月中旬頃に「法定満了喪失予定通知書」、資格が喪失する日以降に「法定満了喪失通知書」の2通を随時ご自宅へ郵送しております。その通知書が資格喪失の証明となりますので、到着後、次の健康保険への加入手続きをご自身でお願いします(国民健康保険の場合は市区町村役場)。
また、返信用封筒が同封されていますので、TJKの「限度額適用認定証・資格確認書」をご返却ください。
※上記いずれの交付も受けていない方は通知書がお手元に届いた時点で手続き完了となります。
任意継続の年間予定表はこちら
- 住所変更の場合 「被保険者住所変更届」を印刷し、必要事項にご記入のうえ、下記送付先までご送付ください。
- 氏名変更の場合 「被保険者氏名変更(訂正)届」または「被扶養者氏名変更(訂正)届」を印刷し、必要事項にご記入のうえ、(交付されていれば)資格確認書と併せて、下記送付先までご送付ください。
「送付先」 〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
東京都情報サービス産業健康保険組合 適用グループ
当組合に下記の書類をご提出ください。
- 「任意継続被保険者資格喪失申出書」※
- TJKの「限度額適用認定証・資格確認書」(交付を受けている方のみ)
- 後期高齢者医療制度に加入したことが分かる書類 (資格情報のお知らせのコピーまたは資格確認書のコピー)
※該当月の前月にTJKから送付される用紙をご利用ください。
下記①②のいずれかの方法で資格喪失が可能です。
①保険料を納付期限までに入金しない
②資格喪失申出書を提出する
詳しくはこちらをご確認ください。
資格証明書の発行
資格証明書 (3)
「被保険者取得日及び資格喪失日証明願」をホームページよりダウンロードいただき、必要事項を記入のうえ当組合へご郵送ください。当組合に到着後、資格証明書を発行し、ご自宅へ送付いたします。
※資格喪失の証明書発行希望の場合、事業所から「資格喪失届」が当組合へ届出されていないと交付できませんので、ご了承をお願いいたします。
当組合に被保険者取得日及び資格喪失日証明願が到着してから、最短で3日~4日後の発送になります。ただし、資格喪失届の(事業所からTJKへ)提出状況や郵便の状況、繁忙時期等の事情により、発行が遅れる事がございますのでご了承をお願いいたします。
40歳になった(介護保険制度に加入)
介護保険 (9)
第2号被保険者である要件が、「市区町村の区域内に住所を有する人」となっているため、海外勤務となったことにより住所を海外に移した場合は適用除外となり、反対に海外勤務者が日本国内の勤務となった場合は介護保険の適用となります。なお、海外勤務となったケースでも、住所がこれまでどおり日本にある場合は適用除外となりません。適用除外に該当、または不該当となった場合は「介護保険適用除外(該当・不該当)届」と添付書類の提出が必要となります。
上記の他に適用除外となるケースとしては、身体障害者療養施設等に入所する方および在留資格3ヵ月以下の短期滞在の外国人等が該当します。
任意継続被保険者に対する介護保険の適用の考え方は、在職中の被保険者とほぼ同じです。ただし、保険料負担については事業主負担がありませんので、全額自己負担となります。また、適用除外届等の届出を本人がTJKに直接していただく必要があります。
健康保険組合が介護保険料を代行徴収するのは、40~64歳の被保険者(第2号被保険者)に限られます。65歳になったら、各市区町村に介護保険料を納付していただきます。
40歳~64歳の健康保険の被扶養者は、介護保険の被保険者にはなりますが、介護保険料は健康保険の被保険者が納める保険料の中に含まれます。被扶養者が介護保険料を納める必要はありません。
育児休業期間中の介護保険料は免除されます。なお、事務担当者による届出により、介護保険料の免除申出があったとみなされます。
必要ありません。TJKで管理している健康保険の被保険者・被扶養者データにより資格の確認をします。なお、介護保険第2号被保険者の資格取得・喪失に関する通知をTJKより該当月の前月に事業所宛に送付しています。
「満40歳に達したとき」とは年齢計算に関する法律等により誕生日の前日を意味しますので、たとえば、誕生日が31日の人は前日の30日が資格取得日、誕生日が1日の人は前月の末日が資格取得日となります。また、「満65歳に達したとき」も同様の扱いとなりますので、誕生日が1日の人は前月の末日が資格喪失日となりますのでご注意ください。
【例】
6月1日生まれの人…5月31日に40歳に達しますので、5月分から健康保険料と介護保険料を負担。
5月31日に65歳に達する場合…上記とは逆に資格喪失月である5月分から健康保険料のみTJKに納付し、介護保険料は市区町村に納付。
健康保険料と同様に納付します。なお、前月から引き続き被保険者であった方が資格を喪失した場合は、喪失した月分の介護保険料は徴収されません。
毎月の介護保険料と同様に、その期間に支給された賞与に対しては保険料の納付が必要となります。10月8日が40歳の誕生日の方には、10月から介護保険料を納付していただきますが、10月中に支給された賞与からも同様に保険料を納付していただきます。また、12月15日が65歳の誕生日の被保険者は12月分の介護保険料の納付は必要なくなり、同様に12月中に支給された賞与からも保険料の納付は必要ありません。
なお、納付していただく際の介護保険料率は月々の料率と同様です。
※ 65歳以上の方は介護保険第1号被保険者となり、お住まいの市区町村に保険料を納付していただくことが必要です。
マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて
マイナンバー(個人番号)の取り扱い (8)
健康保険組合は番号法により、「個人番号利用事務実施者」に指定されており、①番号法第14条第1項(個人番号提供の要求)および②健康保険法第197条(報告等)に基づき、事業主および被保険者にマイナンバーの提供を求めることができます。
ご提供いただいたマイナンバーは、情報提供ネットワークシステムを通じて情報連携を行います。これにより、届出審査時の添付書類の省略やオンライン資格確認開始後にマイナンバーカードを健康保険証として利用することなどが可能となります。
詳細はこちら
マイナンバーの提供を拒んだとしても法的な罰則はありませんが、事業主・健康保険組合におけるマイナンバーの収集は法定義務となっておりますので、その重要性を再度ご説明いただき、ご提供を促していただくようお願いいたします。
原則必要です。
※資格確認書の交付を希望する場合でも、マイナンバーの記載は必須となります。
提出期限は特に設けておりませんが、マイナンバーの登録が遅れることにより、医療機関受診時にオンライン資格確認ができずに事務手続きが遅れることや、行政手続き等において本来省略できるはずの書類の提出が必要になるなど、組合員にとっての不利益が発生する可能性があるため、なるべく速やかなご提出をお願いいたします。
マイナンバーが誤っていることが発覚した場合は、速やかに当組合へご連絡ください。
同日で資格喪失および資格取得を行う場合でも、マイナンバーのご提出をお願いします。
以前、被扶養者だった対象者を再度被扶養者として申請する場合でも、マイナンバーの記載をお願いします。
保険給付について
ベッド数が500床以上の大病院や特定機能病院で受診をする際の初診料に、紹介状を持たずに訪れる患者に対して5,000円を最低金額として特別料金を上乗せできるようになっています。その理由は、高度な医療設備を持つ大病院が風邪など軽い病気の患者で混み合うと、本来の機能を発揮できないためであり、健康保険の対象外となります。
付加給付について
健康保険法に基づき、全国どの健康保険組合へ加入していても一律で受けられる給付を「法定給付」といいます。
法定給付の他にTJKが独自に支給する給付を「付加給付」といい、手厚い給付制度となっています。TJKではみなさまの生活を守るため、可能な限り高いレベルの付加給付制度を維持するよう努めています。
病気やケガで医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示して医療費を支払ったときや、医療費を立て替え払いしたとき、また出産や死亡の際に支給されます。
TJKでは、病気やケガをしたときの「付加金」については自動払でお支払しているため、申請手続きは必要ありません。
ただし、自動払の対象とならない方は申請手続きが必要です。詳細は「手続き方法」を参照ください。
会社の給付金専用口座へ、おおむね受診月の3ヵ月後に自動払されます。その後、会社からみなさまへ給付金を振り分けていただいております。「給付金支給決定通知書」は支給日以降、会社へ郵送しますので会社からお受け取りください。
国や自治体から医療費助成を受けており、自己負担の全部または一部が助成されている19歳以上の方はTJKへ届出をお願いします。
助成内容を確認しTJKからの自動払の全部または一部を停止します。医療費助成を受けているにも関わらずTJKから重複して給付金を受けた場合は、支給した給付金をご返金いただくこととなるため必ずご提出ください。
病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき(高額療養費・付加金)
TJKでは「高額療養費・付加金」を自動払でお支払しているため、申請手続きは不要です。おおむね受診月の3ヵ月後に会社の給付金専用口座へお振込みしますので、会社からお受け取りください。
ただし、自動払の対象でない方は申請手続が必要です。手続き方法を参考に申請してください。
国や自治体から医療費助成を受けており、自己負担の全部または一部が助成されている19歳以上の方はTJKへ「医療費助成制度該当届」に医療証(写し)を添えてご提出ください。助成内容を確認しTJKからの自動払の全部または一部を停止します。
医療費助成を受けているにも関わらずTJKから重複して給付金を受けた場合は、支給した給付金をご返金いただくこととなるため必ずご提出ください。
医療費が高額になったとき(限度額適用認定証)
TJKのホームページから申請書を印刷し、郵送または組合窓口へ提出してください。詳しくは手続き方法を参照ください。
会社を経由せずに被保険者から直接TJKへ申請していただけます。
申請書のみで添付書類は不要です。ただし、被保険者が低所得者のため「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請する場合は非課税証明書(発行日が3ヵ月以内の原本)の添付が必要です。詳しくは手続き方法を参照ください。
組合窓口で申請した場合は、当日窓口でお渡しします。ただし、被保険者以外の代理人が受け取る場合で、委任状欄への記入がなかったり、代理人の身分証明書の提示がないときは窓口でのお渡しができないため郵送による申請と同様の取り扱いとなります。
郵送で申請した場合は、TJKで申請書を受理したのち2~3日(営業日)以内に、簡易書留郵便で発送するため、提出から1週間程度での到着目安となります。送付先はご自宅または申請書に記載した送付希望先となります。
限度額適用認定証は医療費が高額になることが見込まれるときに事前にTJKへ申請していただきますが、医療機関から入院後に指示があった場合はすみやかに申請してください。提出から1週間程度での到着目安となります。なお、送付先はご自宅宛ですが医療機関への直接送付を希望する場合は申請書の「送付希望先」欄に医療機関の所在地・名称、入院をしている病棟番号・部屋番号・氏名を記入してください。あらかじめ医療機関の了解を取り、ご記入ください。
「自己負担限度額」は診療報酬明細書(レセプト)1件ごとに実際にかかった「総医療費」をもとに計算します。診療報酬明細書(レセプト)は人ごと・月ごと・医療機関ごと(医科・歯科、入院・外来別)であるため、複数の医療機関で入院をした場合は医療機関ごとに「自己負担限度額」までのお支払が必要となります。
限度額適用認定証は、医療機関へ提示後に返却されますので1枚作成すれば有効期限内は何度も使用することができます。複数枚作成する必要はありません。
限度額適用認定証は破棄せずTJKにご返却ください。継続して使用する場合は返却とともに再度申請書を提出してください。
高額療養費の特例(特定疾病療養受療証)
TJKのホームページから申請書を印刷し、郵送または組合窓口へ提出してください。詳しくは手続き方法をご参照ください。
資格確認書等を持たずに医療機関を受診したとき
「診療明細書」は、「診療報酬明細書(レセプト)」ではありません。記載内容が異なるため、代用することができません。「療養費」を申請する際は、必ず医療機関で「診療報酬明細書(レセプト)」の発行を依頼し、添付してください。
申請書は1枚で、病院と調剤薬局それぞれの領収書、診療報酬明細書(レセプト)を添付してください。
月別、受診者別、医療機関別(入院・外来別)でそれぞれ申請書の作成が必要です。この場合、2月の妻分・2月の子分、3月の妻分・3月の子分で計4枚の申請書が必要です。
TJK加入前の資格確認書等を使用してしまったとき
資格確認書等は手元にあればいつでも使用できるわけではないため、TJKに加入した日以降はTJKの資格確認書等を使用してください。誤って以前の資格確認書等を使用した場合は、以前の健康保険組合が立て替えた医療費を返還し、TJKへ「療養費」として請求してください。詳しい手続きはこちらを参照ください。
医療機関の窓口で交付された「領収書」や「診療明細書」は提出する必要がありません。以前の健康保険組合へ7割または8割を返金したことが確認できる「領収証」と「診療報酬明細書(レセプト)」を提出してください。返還したにも関わらず「診療報酬明細書(レセプト)」が郵送されない場合は、別途、発行依頼の手続きが必要な場合がありますので、以前の健康保険組合へお問い合わせのうえ交付を受けてください。
治療用装具をつくったとき
小児の治療用眼鏡をつくったとき
いかなる理由があっても使用年数を経過していない場合は再度「療養費」として請求することはできません。使用年数を経過せずに作成した眼鏡の費用は全額が自己負担となります。
「療養費」の対象となる治療用眼鏡の給付額には上限額があり、38,902円(令和元年9月30日購入分までは38,461円)です。眼鏡の作成費用が上限額を超えた場合であっても、年齢により上限額の7割または8割相当額の支給となるため、高価な眼鏡を作成した場合の実費と上限額との差額は自己負担となります。
治療用眼鏡は対象病名のみ請求することができます。「弱視」「斜視」「先天性白内障術後の屈折矯正」以外は対象外であるため、「近視」「乱視」のみの場合は請求することができません。
接骨院・整骨院で施術を受けるとき
接骨院・整骨院で健康保険が使用できるケースは限られており、「急性・亜急性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)・骨折・脱臼」の場合のみです。今回の「肩こり」はいずれにも当てはまりませんから、健康保険を使用することができません。施術師へ再度、痛みの原因を伝え全額自費で支払いましょう。3割負担のままにしておくと、後日TJKの調査によりみなさまからTJKが負担した施術費用(総額の7~8割)をご返金いただく場合があります。
長期的に施術を受けたのちに以上のことが判明すると、高額な費用を返金しなければならなくなりますので、早めに自費での支払へ切り替えるようにしましょう。
はり・灸、あん摩・マッサージの施術を受けるとき
健康保険を使ってはり・灸の施術を受けるときは、医師の同意を得て施術を受けることになります。主として慢性病で「保険医療機関等で療養の給付を受けても所期の効果が得られなかったもの、または今までに受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていない」場合に、はり・灸の施術を行うことにより、治療上の効果が得られると医師が認めた場合、6ヵ月を限度としてかかることができます。
業務上・通勤途上の病気・ケガは労災保険で
このような場合は、通勤のためにやむを得ずにとった合理的な経路上のケガと認められるため、健康保険ではなく通勤災害として労災保険で診療を受けることになります。
病気やケガで仕事を休み、給与が得られないとき(傷病手当金)
傷病手当金1回目の支給時は、療養のため労務不能となり、連続して3日間休んだのち、第4日目より給付が開始されます。この連続した3日間の休みを「待期」といい、この間は傷病手当金の給付は受けられませんが、請求期間には待期3日間も含めて記入してください。
待期は連続した3日間の休みをもって完成しますので、「1日・休み、2日・休み、3日・出勤、4日・休み、5日・休み」といった場合、待期が完成していませんので、第4日目の休みに対しても、傷病手当金は支給されません。
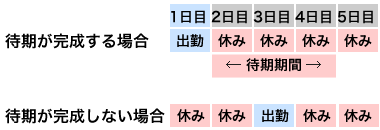
傷病手当金の支給額は、被保険者の受ける報酬に基づいて算定された、「標準報酬月額」より算出されます。
支給開始日を含む、直近の12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額 が傷病手当金の1日当たりの給付額となります。
ただし、傷病手当金の請求期間中の分として、事業主等より一部でも報酬(給与)の支払いを受けた場合は調整され、傷病手当金の支給額が減額されます。すなわち、給与(標準報酬月額)の3分の2相当額が事業主等より保障されている場合、傷病手当金の給付はありません。
同一の傷病で給付を初めて受けた日から、規定に基づいた日数分を支給します。支給開始日によって、支給期間および満了日の考え方が異なります。
【①支給開始日が令和2年7月1日以前の場合】
支給開始日から起算して1年6か月の日付までの連続して経過する期間が支給期間です。途中で就労した期間も含めるため、傷病手当金の給付を受けた日の合計が1年6か月ということではありません。
【②支給開始日が令和2年7日2日以降の場合】
支給開始日から1年6か月の日付までの日数が総支給日数です。ただし支給期間は通算しますので、途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合、再び療養のために欠勤となったときに残りの支給日数も支給可能です。
なお、①と②共通で、途中で病院等を変わり傷病名が変わった場合でも、前回からの関連傷病とみなされる場合は、前回支給開始時からの継続となります。支給期間が新たに付与されることはなく、給付を受けられる期間は変わりません。
また、療養の給付状況や病状経過等により、労務不能と判断できないときは支給期間の途中であっても給付を打ち切られる場合もあります。
会社から給与が支給されないときに生活保障給付として請求することができる給付金であるため、有給休暇を取得したときは請求することはできません。ただし、会社から給与の全部または一部が支給されているときに、TJKから支給される傷病手当金の日額と有給休暇の日額を比較し傷病手当金のほうが金額が多いときは、差額を請求できます。傷病手当金の日額については傷病手当金の支給額を参照ください。
傷病手当金は疾病に対する療養の給付(医療機関等での治療・投薬等)を行い、療養に専念した上で病気やケガを治し、労働力を早期に回復することを主な目的としています。医療機関等を受診せずに自宅で安静にしていたときは療養の給付が認められないことから、傷病手当金は請求対象外となります。
健康保険法により「被保険者が現に属する保険者等(=TJK)により定められた標準報酬月額に限る」とあることから、個人の希望、会社都合を問わず他の社会保険の標準報酬月額を通算することはできません。「計算方法2」の①②いずれかにより計算することとなります。
差額を請求することができるのは、請求期間中に会社を休んでおり、休んだ日に会社から支給された給与の日額と傷病手当金の日額を比較し傷病手当金のほうが金額が多い場合です。出勤し給与が支給されている日については支給額に関わらず請求対象外となります。
TJKの資格を喪失した後も傷病手当金を請求するときは、【資格喪失後の要件】を全て満たす必要があります。要件「2」に記載があるとおり退職日に出勤をしたときは請求期間が継続されないことから資格を喪失した後の期間は請求対象外となります。
TJKの資格を喪失した後も傷病手当金を請求するときは、【資格喪失後の要件】を全て満たす必要があります。要件「2」に記載があるとおり在職時から傷病手当金の請求期間が継続する方が対象です。任意継続被保険者となって以降に新たに傷病手当金を請求することはできません。
TJKの資格を喪失した後も傷病手当金を請求するときは、【資格喪失後の要件】を全て満たす必要がありますが、「TJKの任意継続被保険者であること」という要件はありません。そのため、任意継続被保険者として継続加入した場合、国民健康保険に加入した場合いずれであっても【資格喪失後の要件】を満たしていれば引き続きTJKに傷病手当金が請求できることとなっています。
1枚でご請求いただけます。ただし、退職日までは事業主の証明が必要なため、提出時点で退職していても必ずお勤めされていた会社へ提出してください。
入院したときの食事(入院時食事療養費)
50,000円の内訳は、治療費の一部負担額21,440円+入院時の食事の標準負担額28,560円(510円×56食)となります。
入院時の食事の標準負担額は付加金の対象となりません。付加金の対象となるのは、治療費の一部負担額だけですので、24,240円から20,000円を差し引いた1,400円(100円未満切捨)だけとなります。
海外の医療機関で受診したとき(海外療養費)
「海外療養費」を請求することができます。手続き方法を参考にお手続きください。
業務上や通勤途上の災害による病気やケガは、日本国内と同様に健康保険の対象外です。お勤めの事業所を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。
治療を目的として海外へ渡航し、治療を受けた場合は健康保険の対象外です。医療費は全額自己負担となります。
診療内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)は日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を算出するために必要な書類で、現地の医師に証明を依頼する必要があります。書類が用意できない場合は「海外療養費」を請求することはできないため、帰国後に現地の医師へ証明を依頼することが現実的に困難であるときは、事前に印刷し渡航先へ持参してください。
また、海外は自由診療のため、海外で医療機関を受診する場合、日本国内と同じ病気やケガでも国や医療機関によって請求額が大きく異なります。「海外療養費」の支給額は、みなさまが実際に支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも支給額が大幅に少なくなる場合があります。
必要に応じて、民間の海外旅行保険等へ加入し、万が一の医療費負担を軽減しましょう。
民間の海外旅行保険から保険金が給付される場合であっても「海外療養費」を請求することができます。
手続き方法はこちらをご参照ください。
自己負担額が公費負担となるとき
年齢、病気の種類、患者の状態等によりさまざまな公費負担による医療費助成があります。対象と思われる方は、内容に応じて主治医またはお住まいの自治体窓口などへお問い合わせください。
TJKへ「医療費助成制度該当届」に医療証(写し)を添えてご提出ください。TJKではみなさまが医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示して医療費を支払った場合に、その医療費が一定額以上であると「高額療養費・付加金」をお支払いします。
「高額療養費・付加金」は基本的にみなさまから申請をいただかずTJKから会社へ自動払しております。「公費負担」により自己負担の全部または一部が助成されている方は、助成内容を確認しTJKからの自動払の全部または一部を停止します。
医療費助成を受けているにも関わらずTJKから重複して給付金を受けた場合は、支給した給付金をご返金いただくこととなるため必ずご提出ください。
出産手当金を受けるとき
出産手当金は、女性被保険者が出産のために仕事を休み、会社から給与が支給されないときに生活保障給付として請求することができる給付金です。被扶養者として加入している方は請求対象外となります。
計画分娩等で出産予定日が当初と変更となった場合でも、初回健診時に医師または助産師から伝達された予定日を記入してください。また「被保険者の記入するところ」と「医師または助産師が意見を書くところ」の出産予定日の記入が同一であることを提出する前にご確認ください。
出産手当金は、基本的に産前・産後の請求期間が終了し、請求期間中の出勤簿・賃金台帳の準備ができてからのご提出となります。ただし、例外として産前期間(出産日まで)と産後期間を分け、別々に請求することもできます。この場合はそれぞれの期間の出勤簿・賃金台帳が準備できてからのご提出となります。
交通事故や傷害事件に巻き込まれたとき
交通事故に巻き込まれた場合、医療費などすべての損害を加害者に請求するのは当然です。しかし、ケガの治療は急を要しますし、加害者との話し合いには時間が必要な場合が多いものです。
このようなケースでも、健康保険で治療を受けることができます。ただし、この場合はすぐに第三者行為相談室に事故による治療を受けたことを連絡し、必要書類を提出してください。この届出があって、初めて健康保険組合は交通事故によるケガであることを知り、加害者に健康保険組合が支払った医療費などを請求することができるからです。
本来、加害者が支払う医療費をTJKが支払えば、そのお金はもともとみなさまからの保険料などですから、それをムダに使うことになります。
後日、交通事故であることがわかり、加害者から損害賠償を受けていたり、免責していたりするような場合は、TJKは被害者であるご本人に治療費等を請求することもあります。
死亡したとき
他の社会保険や国民健康保険等に加入している家族が死亡したときに、TJKへ「家族埋葬料」「家族埋葬料付加金」を請求することはできません。死亡した方が死亡時に加入していた健康保険へ請求してください。
「埋葬料」は一律で50,000円、「埋葬料付加金」は死亡時の標準報酬月額1ヵ月分を支給します。
ただし、上限額(360,000円)を上回る標準報酬月額であった場合は上限額360,000円の支給となります。
| 埋葬料(法定給付) | 埋葬料付加金(付加給付) | 合計給付額 | |
|---|---|---|---|
| 死亡時の標準報酬月額が 240,000円であった場合 | 50,000円 | 240,000円 (標準報酬月額1ヵ月分) | 290,000円 |
| 死亡時の標準報酬月額が 520,000円であった場合 | 50,000円 | 360,000円 (上限360,000円より) | 410,000円 |
「埋葬費」は埋葬料50,000円の範囲内での実費、「埋葬費付加金」は埋葬料付加金の範囲内で、葬儀に要した実費から埋葬料50,000円を除いた額となります。「埋葬費付加金」の支給額については下記表の欄外※1・2を参照してください。
| 埋葬費(法定給付) | 埋葬費付加金(付加給付) | 合計給付額 | |
|---|---|---|---|
| 死亡時の標準報酬月額が 240,000円であった場合 | 50,000円 (埋葬料の範囲内の実費) | 240,000円(※1) | 290,000円 |
| 死亡時の標準報酬月額が 520,000円であった場合 | 50,000円 (埋葬料の範囲内の実費) | 300,000円(※2) | 350,000円 |
※1 実費-埋葬費(350,000円ー50,000円=300,000円)または標準報酬月額1ヵ月分(240,000円)のいずれか低いほうとなります。
※2 実費-埋葬費(350,000円ー50,000円=300,000円)または標準報酬月額1ヵ月分(ただし上限360,000円)のいずれか低いほうとなります。
自殺の場合も請求することができます。請求書内「死亡した原因」欄は具体的な死因を記入してください(例:溺死・縊死等)。
「埋葬料」を請求することができます。ただし死産であった場合は支給対象外となります。
次の要件のいずれかに該当している場合は「埋葬料」または「埋葬費」を請求することができます。
- 被保険者が資格喪失後、3ヵ月以内に亡くなったとき
- 被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき
- 被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後、3ヵ月以内に亡くなったとき
ただし、上記の要件を満たしていても資格喪失後に新たに加入している社会保険や国民健康保険等へ埋葬料、葬祭費などを請求する場合は、重複してTJKへ「埋葬料」や「埋葬費」を請求することはできません。
また、資格喪失後の「埋葬料」や「埋葬費」は法定給付のみの支給となるため、付加給付は支給されません。