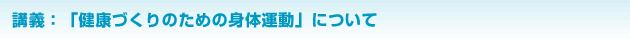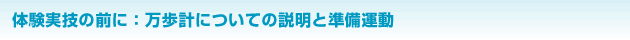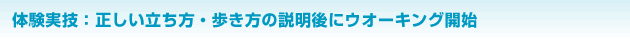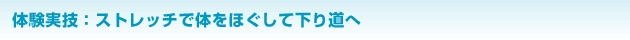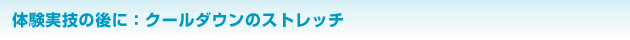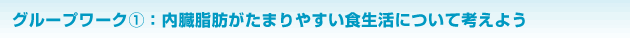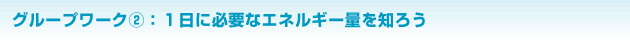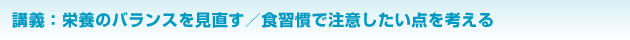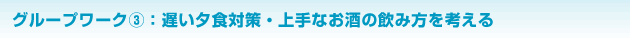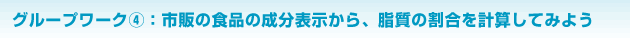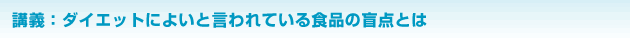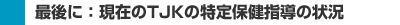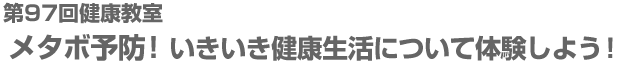
平成21年11月12日(木)~13日(金)、直営保養所「アルペンドルフ白樺」において、第97回健康教室を開催しました。今回は宿泊型健康教室で、1日目には第一部としてTJK健康運動指導士による講義と体験実技、2日目には、第二部としてTJK管理栄養士による講義とグループワークが行われました。その様子をレポートします。
第一部 効果的な運動の方法
●講師 笠原 千秋(TJK健康運動指導士)
体験実技に先立って行われた講義では、厚生労働省から出されている『健康づくりのための運動指針2006』(PDF)に基づいた身体活動の目標が示されました。

「身体活動」とは、身体を動かすことの総称であり、「運動」と「生活活動」が含まれます。そして、身体活動量(単位:エクササイズ)=身体活動の強さ(単位:メッツ)×時間(単位:時間)であり、1週間で23エクササイズが必要とされています。
なお、「1週間で23エクササイズ」といっても、土日などにまとめて体を動かすのではなく、「1日3~4エクササイズ」を目安とし、さらには、23エクササイズのうち4エクササイズは「活発な運動」であることが望ましいとされています。
ただし、「4エクササイズの運動」は、生活習慣病やメタボリックシンドローム予防のための目安であって、すでにメタボリックシンドロームや生活習慣病になっている人では、「10エクササイズの運動」が必要です。
「4エクササイズの運動」の一例を挙げると、ウオーキング(時速6km)やアクアビクス・水中歩行は4メッツですから、1時間行えば、4エクササイズとなります。有酸素運動はできれば20分以上続けることが望ましいので、一度に時間が取れなくても、最低20分間の運動を週3回行うことを目標にするとよいでしょう。
また、運動の効果は3日間続くと言われています。毎日継続できなくても、週2~3回行えば運動の効果は現れます。自分の生活習慣にうまく運動を組み合わせることが、週23エクササイズを実現するコツです。そして、運動を継続するには、例えば、体重を減らす、肩こり解消など、「自分には何のために運動が必要なのか」という理由を考え、その目的に合った運動を選ぶと効果的です。

講義後には、体験実技として、ウオーキングによる周辺散策が行われました。
受講者には、それぞれ、万歩計とペットボトルの水が配られ、万歩計の設定・装着方法および水分補給について説明がありました。
水分補給については、以下の注意がありました。
(1)運動前に1~2口水を飲んでおく。
(2)運動中には、夏なら15~20分に1回、冬なら30分に1回を目安にする。
(3)足がつるのは脱水症状が原因の場合もあるので、十分な水分補給を心がける。
次に、体を温める準備体操として、以下のストレッチが室内で行われました。姿勢を10秒以上保持する、息を止めないで楽な呼吸を続ける、痛みが出ない程度に行う、などがストレッチのポイントです。

(1)頭の上で手を組み、手のひらを返して伸び上がる。その状態から横にゆっくりと倒す。反対側にも倒す。
(2)歩幅を広げて(1)の伸びをし、片側に体をひねる。反対側にもひねる。
(3)片方の腕を伸ばして前に出す。反対側の腕でひじの外側から引き寄せる。腕を替えて行う(五十肩の防止にもなるストレッチ)。
(4)片方の腕を上に伸ばして、ひじから曲げる。反対側の手でひじを下に押す。腕を替えて行う。
(5)足を広げ、前屈。
(6)足を前後に広げ、前の足の太ももに両手を置き、前に体重をかけてアキレス腱を伸ばす。足を替えて行う。
(7)椅子の背もたれを左手で持ち、右足を後ろに曲げて右手で持つ。反対側も行う(膝痛予防のストレッチ)。
(8)足首を片足ずつ右回しと左回しをゆっくり行う。足を替えて行う。
(9)深呼吸。

戸外に出たところで、正しい立ち方、ウオーキングの際の歩き方の説明がありました。
正しい立ち方は、つま先を正面に向け、膝-腰-耳がまっすぐになるように立ち、腹筋に力をいれます。
歩き方は、歩幅を広く取り、かかとから柔らかく着地します。上から引っ張られるように背筋を伸ばし、腕を後ろに大きく引くことを意識して腕を振ります。
以上を実践した後に万歩計をゼロに設定し、アルペンドルフ白樺前から出発しました。コースは、まず一般道から八子ヶ峰公園までの坂を上り切った後に、一転して坂を下って白樺湖に至る、約1時間弱の行程です。
アルペンドルフ白樺の敷地内から一般道路に出たところから上り道になります。「通常のウオーキングよりも歩幅を狭く取ること」「重心を後ろにかけすぎないこと」という上り道での注意と、「汗をかきたい人は、ペースは同じでも腕を大きく振るだけで運動強度が上がる」とのアドバイスがありました。
歩き始めてから10分後、万歩計の歩数を確認すると、人によって多少は異なりますが、すでに全員が1,000歩を超えていました。「これぐらいのペースで歩き続けるように」と指示がありました。

歩き始めてから15分後、八子ヶ峰公園に到着。ここからは下り道になるため、体をほぐすために以下のストレッチが行われました。
(1)両手を体の前に伸ばして、できるだけ早くグーパーをする。
(2)両腕を上方から横に、大きな円を描くように回す。
(3)骨盤を回す。反対方向にも回す。
(4)両足を横に大きく広げ、片足を曲げて、片足を伸ばす。足を替えて行う。
(5)両足を外側に曲げて、膝に手を当て、肩を入れる。反対方向も行う。
(6)深呼吸。
下り道は、一般道ではなく、信濃路自然遊歩道を歩きます。下り道の歩き方として、「上り道よりもさらに歩幅を狭める」「ブレーキをかけるような歩き方では膝痛を起こすので、かかとからゆっくり着地して、膝に負担をかけないように」と、注意がありました。

信濃路自然遊歩道を下ると、「白樺湖Royal Hillスキー場」を横切ります。本来は白樺湖を望むビューポイントですが、午後からガスが白く巻いてしまったために、この日は景観を楽しむことはできませんでした。しかし受講者たちは、小石交じりの道に気をつけながらも、軽快に下っていきました。
再び一般道へ。ホテルや食事処が並ぶ道路をさらに下り、白樺湖畔に到着したのは、歩き始めてから40分後。白樺湖を左手に見ながら平地を少し歩き、パーキングで出迎えのバスに乗り込みました。車では、アルペンドルフ白樺までは10分弱でした。

アルペンドルフ白樺に戻ってから、筋肉痛を起こさないために、以下のクールダウンのストレッチが行われました。
(1)立って、片足ずつ足首を外側と内側に倒す。足を替えて行う。
(2)かかとができるだけ遠くを通るように、足首を片足ずつ回す。足を替えて行う。
(3)椅子に座り、少し前かがみになって、片足ずつひざの後ろを伸ばす。
(4)腿をぐりぐりとマッサージする。
(5)片方の膝の裏を両手で3秒間圧迫し、ゆっくり力を抜く。2回繰り返す。足を替えて行う。
(6)靴を脱いで、膝の上に片方の足を乗せ、足のマッサージを行う。下からすり上げる、指を1本ずつ引っ張る、かかとからアキレス腱までをすり上げる。足を替えて行う(リンパの流れをよくするマッサージ)。
(7)アキレス腱からふくらはぎまでをすり上げる。足を替えて行う。
(8)足をブラブラと揺らす。次に、前後にパタパタと足踏みする。
(9)深呼吸。
14時30分の講義から、準備体操を経て体験実技を行い、クールダウンをもって、第一部は16時15分に終了しました。
第二部
Stop!! メタボ 賢い食事法で無理なく内臓脂肪を減少させよう
●講師 宗本乃里子(TJK管理栄養士)
第二部では、グループワークを中心とした講義が行われました。1グループは男女2人ずつの計4人で、6グループ。グループには、さまざまな年代の人が混じるように構成されています。メンバー同士で挨拶を済ませた後、講義が開始されました。

まず、メタボリックシンドロームの原因の一つである内臓脂肪がたまりやすい要因について以下の7項目が挙げられました。
(1)肥満
(2)閉経後
(3)30歳以上の男性
(4)喫煙者
(5)運動嫌い
(6)日常の動きが少ない
(7)間食や夜食の習慣
8番目の項目として、「内臓脂肪がたまりやすい食生活」をグループごとに考えることにしました。グループでの討議後に、管理栄養士が挙げたのは以下10項目です。
(1)満足するまで食べる
(2)早食いである
(3)残り物をつい食べてしまう
(4)野菜が不足している
(5)炭酸飲料など甘い飲み物が多い
(6)炭水化物の重ね食いが多い(ラーメンとチャーハンなど)
(7)間食が多い
(8)夜の食事が遅い
(9)濃い味付けが好きである
(10)飲みすぎ、または休肝日がない
このほかに、グループで考えられた内容が発表され、「脂肪分が多い」「ファーストフード・インスタント食品を多く食べる」「好き嫌いが多い」「朝食を食べない」などが挙げられました。
次に、食事からの摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスから考えると、メタボとは「摂取エネルギーが消費エネルギーを上回っている状態」であり、メタボ解消のためには、摂取エネルギーを減らして、運動や生活活動による消費エネルギーを増やせばよいことが示されました。
適正体重を保つためのポイントは、以下3点です。
(1)1日の食事量を見直す。
(2)栄養のバランスを見直す
(3)食習慣を見直す
1日の食事量を見直すためには、必要なエネルギー量を知る必要があります。
以下の数式を基に、1日に必要なエネルギー量を各自で計算しました。
| 標準体重 ※1 (kg) |
× | 基礎代謝基準値 ※2 (kcal/kg/日) |
× | 身体活動レベル ※3 |
= | 1日に必要な エネルギー量 (kcal/日) |
※1 標準体重
身長
(m)×身長
(m)×22=標準体重
(kg)
※2
基礎代謝基準値
(kcal/kg/日)
| 年齢区分 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 18~29歳 | 24.0 | 22.1 |
| 30~49歳 | 22.3 | 21.7 |
| 50~69歳 | 21.5 | 20.7 |
| 70歳以上 | 21.5 | 20.7 |
※3
身体活動レベル
*身体活動レベルの目安
低い : デスクワークなどほぼ1日座りっぱなし
普通 : 座っていることが多いが、通勤や買い物などで多少は歩く
高い : 1日を通してよく歩く。週末に運動をする
| 低い(レベルⅠ) | ふつう(レベルⅡ) | 高い(レベルⅢ) | |
|---|---|---|---|
| 18~29歳 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| 30~49歳 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| 50~69歳 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| 70歳以上 | 1.45 | 1.70 | 1.95 |
身長や年齢・性別、身体活動レベルによって、それぞれに必要なエネルギー量は異なりますが、デスクワークをしている人のだいたいの目安は、男性では1,800~2,200kcal/日、女性では1,600~1,800kcal/日になります。
最近、コンビニやスーパー、レストランなどでは、食品のエネルギー表示を行っているところが増えています。自分の1食のエネルギー量の目安を知っていれば、食品を購入したり、注文したりするときに、自分に合った食品を選ぶのに役立ちます。1食のエネルギー量の目安は、以下の数式で求められます。
| 1日に必要なエネルギー量 (kcal/日) |
÷3 | = | 1食のエネルギー量の目安 (kcal/日) |
次に、標準体重の代わりに自分の現在の体重を入れ、同様に1日に必要なエネルギー量を計算し、標準体重を入れた場合のエネルギー量と比較しました。例えば、標準体重から測定したエネルギー量が2,000kcalで、自分の体重から測定したエネルギー量が2,500kcalだとしたら、500kcal食べすぎていることになり、それをどこで減らすかを考えなければいけません。
比較の結果を確認したところ、受講者はさすがに健康管理委員として日々実践されているためか、必要なエネルギー量を大幅に超過している人は少なく、女性では逆に体重から計算したエネルギー量のほうが少ないという人も見られました。
栄養のバランスを見直すためには、食事は「主食・主菜・副菜」を基本とし、主食はご飯・パン・麺、主菜は肉・魚・大豆製品・卵、副菜は野菜・海藻・きのこなどから選ぶこと、そしてその他に果物と乳製品を取り入れると、1日の栄養のバランスが取りやすくなります。
また、食習慣を考えるうえで、TJK組合員の朝食の欠食率を見ると、男女いずれも全国平均より高くなっています(下表参照)。
■朝食の欠食率(平成18年度統計)
| TJK(30代以上) | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 男性 | 20.0% | 13.0% |
| 女性 | 11.3% | 8.6% |

この欠食率の高さは、おそらく、「遅い夕食」がその原因となっていると考えられます。さらに、遅い時間に夕食を摂ると、「朝食欠食→空腹時間が長い→昼食にドカ食いしてしまう→遅い夕食」という悪循環を引き起こしてしまいます。
夜遅い食事だと内臓脂肪がたまりやすい理由には、体内に脂肪をためる指令を出すB‐MAL1という物質が22時から深夜2時までの時間帯に分泌されることが挙げられます。
また、空腹時間が長いと、一種の飢餓状態になって、内臓脂肪をため込みやすくなります。したがって、1日に同じ2,000kcalを摂る場合でも、「500kcal+800kcal+700kcal(1日3食)」に比べ、「1,000kcal+1,000kcal(1日2食)」では、内臓脂肪をため込みやすくなるので、1日3食でリズムを整えることが大切です。
全員で教室の中央に集まり、さまざまな食品や食事メニューの写真を使いながら、遅い夕食対策と上手なお酒の飲み方について話し合いました。
●夕食の上手な摂り方
まず、遅い夕食対策として夕食の上手な摂り方が管理栄養士より示されました。受講者は食品の成分表示などを確認し、それぞれのアドバイスの根拠が納得できたようでした。

(1)夕食を2回に分け、夕方に主食となる炭水化物を摂り、帰宅後はおかずだけを食べる。炭水化物は内臓脂肪をためやすくなるが、ゼロにする必要はなく、早い時間に食べておくとよい。
(2)遅い夕食をセーブするコツは、早い夕食に腹持ちのよいものを食べること。
・麺類はうどんならよいが、ラーメンではカロリーが高い。
・パンは、ご飯に比べると腹持ちが悪い。特に菓子パンはパンというよりお菓子であり、2つ食べればほぼラーメンと同カロリーとなるので、間食にしてはカロリーが多すぎる。間食なら200kcalを目安とする。
(3)早い夕食には、おにぎり、クラッカー、シリアルバー、春雨スープなどがおすすめ。
(4)早い夕食時に一緒に摂る飲み物は、牛乳、豆乳、トマトジュース・野菜ジュースなどがおすすめ。糖質(炭水化物)と甘いものを同時に摂ると、一気に血糖値が上がった後に急激に下がるので空腹感が大きく、帰宅後のドカ食いの原因になるため、甘い飲み物は控える。
(5)缶コーヒーのエネルギー量をスティックシュガーに換算すると7本分もの砂糖が含まれている。
(6)「カロリーオフ」と表示されている飲み物は100mlあたり20kcal以下のエネルギー量があるので、「カロリーゼロ」ではない。
●遅い夕食が避けられない場合は
次に、遅い夕食が避けられない場合は、どのように摂ったらよいかを全員で考えました。まず、食事の順番を考えると、真っ先に摂るものとして汁物が挙げられました。水分は胃を膨らませるので、ドカ食いを防ぐのに役立ちます。そして、主菜は油の少ない献立にして、腹七分目を心がけることが大切です。
●お酒はどう飲んだらいい?
お酒を飲む場合は、主食は食べない、副菜をおつまみにして主菜を食べない、などの案が受講者から挙げられました。
管理栄養士からは、「お酒もおつまみも好きな人は太る」「脂肪分の多いおつまみは脂肪肝の原因になる」との指摘があり、スナックをおつまみにする場合は小袋のものを選ぶ、お酒は寝酒にはしない、などのアドバイスがありました。
「例えば、ビールならおいしいと思えるのは最初の1本だけでは? その後の2~3本を惰性で飲んでしまっているなら、おいしいと思える1本でやめられるとよいですね」という言葉にうなずく受講者の姿も見られました。
次に、市販の食品の選び方について考えました。コンビニやスーパーで買うお弁当やサンドイッチは、成分表示がされているものがほとんどです。食品を選ぶときには、カロリー(熱量)とともに、脂質の割合にも注意することが大切です。そこで、実際に売られている下記8項目の食品について脂質の割合をグループで計算することにしました。
脂質の占める割合は、以下の数式で求められます。脂質の占める割合は25%以下、さらに言えば18~20%程度が望ましいとのことでした。
脂質の占める熱量(kcal)[=脂質(g)×9] ÷ 総熱量(kcal) ×100= 脂質の占める割合(%)
表 8種類の食品の熱量と脂質および熱量と脂質から計算した脂質の割合
| 食品名 | 総熱量 | 脂質 | 脂質の割合 |
|---|---|---|---|
| (1)ツナと海老のサラダ巻き | 362kcal | 7.1g | 17.6% |
| (2)炭火焼牛カルビ弁当 | 743kcal | 17.6g | 21.3% |
| (3)幕の内弁当 | 710kcal | 18.8g | 23.8% |
| (4)ハム野菜サンド | 235kcal | 12.5g | 47.9% |
| (5)トマトソースのパスタ | 504kcal | 10.5g | 18.8% |
| (6)チャーハンとねぎダレ山賊焼き弁当 | 1,126kcal | 44.2g | 35.3% |
| (7)きのこづくし弁当 | 653kcal | 16.8g | 23.2% |
| (8)照りマヨチキンロール(惣菜パン) | 339kcal | 20.6g | 54.6% |

見た目からは、脂質の割合が高いと考えられたのは、(2)炭火焼牛カルビ弁当、(6)チャーハンとねぎダレ山賊焼き弁当、といったところですが、グループでそれぞれ計算したところ、意外な結果となりました。
最も脂質の割合が高かったのは、(8)照りマヨチキンロール(惣菜パン)で、エネルギー量の半分以上を脂質が占めていました。2番目は、(4)ハム野菜サンドです。この2つに共通しているのは、マヨネーズが使われていること。パンは腹持ちがよくないとの指摘がありましたが、このような点にも注意すべきことがわかりました。
また、塩分は通常、Na(ナトリウム:単位mg)として表示されている場合が多いのですが、Na(mg)×2.54÷1,000=塩分(g)となります。先に挙げた8種類の食品のうち、最も塩分量が多かったのは、(6)チャーハンとねぎダレ山賊焼き弁当で、塩分量は8gでした。1日の塩分摂取量は10g以下が望ましいとされていますが、その数値から考えると高い塩分量であることがわかりました。
ダイエットによい、ヘルシーと言われて話題になった食品には下記8項目などが挙げられますが、同時に注意すべき点もあります(下表参照)。
つまり、ダイエットによい、ヘルシーと言われている食品にも、さまざまな盲点があり、また体によいと言われているものでも、一般に摂りすぎはよくありません。そして、ダイエットを考えるにあたっては、体重が増えた理由はそれぞれに違うので、 それはなぜなのかと振り返り、自分でできる解消法を見つけて、継続することが大切です。
| 食品名 | 注意点 |
|---|---|
| (1)牛乳・ヨーグルト・チーズ | カルシウムが多いものの3つは摂りすぎ。 |
| (2)オリーブ油・植物油 | 他の油をオリーブ油に替えるのはよいが、わざわざ飲む必要はない。 |
| (3)豆腐・納豆・きな粉 | 3つは摂りすぎ。豆腐には植物性だが脂質も含まれているので、意外とカロリーが高い。 |
| (4)はちみつ・黒砂糖・みりん | 砂糖は砂糖なので、摂りすぎない。 |
| (5)ココア | チョコレートはココアを脂肪で固めたもの。チョコレートはココアの代わりにはならない。 |
| (6)青背の魚 | よい油が含まれているが、摂りすぎるとカロリー過多に。サンマなら3分の1匹が適量。 |
| (7)ブルーベリージャム | 単なるジャムなので、目によいというわけではない。 |
| (8)ソーメン | ヘルシーと思っても、量を食べればそれなりのカロリーになる。 |
最後に、現在のTJKの特定保健指導の状況が報告されました。直営健診センターで平成20年10月から21年1月末までに特定健診を受診した人の特定保健指導状況では、保健指導の支援完了者は35%。この数値を平成24年度には45%にまで引き上げる必要があります。
厚生労働省によって設定された目標値の達成度に応じて、医療保険者が支払う後期高齢者医療制度への支援金が加算・減算されるため、TJKのペナルティーの最大加算額は19億円と想定されています。つまり、健保財政ひいては健康保険料にも大きな影響を及ぼすことになるのです。
TJKでは30代での肥満率が30~31%。40歳になってから気をつけるのではなく、20代・30代からメタボにならないことが大切であることが示されました。
また、特定保健指導については、支援中の脱落者が多く、保健指導スタッフがメール・電話・手紙など、本人が選んだ手段で継続的な支援を行っても返事が来なくなる場合が多いので、健康管理委員の受講者に対して「何かよいアイディアがあればご協力いただきたい」との要望が出され、第二部を終了しました。
健康教室の第二部は、グループワークが中心であったため、より実践的な内容であったとともに、アドバイスの根拠が確認でき、受講者からも積極的に質問やアイディアが出されたりと、充実した内容となりました。
お問い合わせ先:東京都情報サービス産業健康保険組合 健康管理グループ TEL 03-3360-5951
COPYRIGHT(C) 2008, 東京都情報サービス産業健康保険組合 ALL RIGHTS RESERVED.